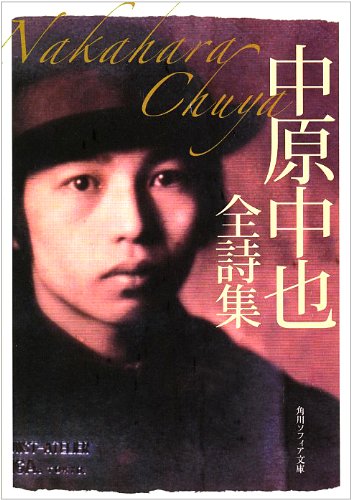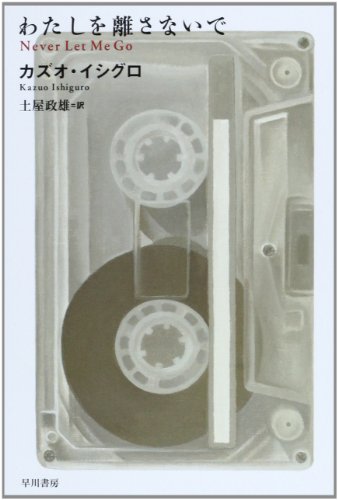『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は2013年に出版された村上春樹さん13作目の長編小説です。
この作品は、その謎めいたタイトルが発売前から大きな話題となり、また、前作の『1Q84』が大ヒットしたことも手伝って、なんと発売から7日間で100万部を売り上げました。
ブームにのせられて買った人たちは…
最終的に2013年年間ベストセラーの総合2位にまで輝き、売れに売れた小説のはずが、読後に「良かったよ!」と感想を語っている人をあまり見かけません。
当時、村上春樹に免疫がないにもかかわらず村上ブームにのせられてこの小説を買ってしまった人達は、ページを開いてみて、こう思ったのではないでしょうか。
「なんて退屈な小説なのだろう」
そして、とばしとばしに半分まで読んだ所で、あるいは、パラパラと最後までめくってみた所で、そのまま小説を閉じてしまったかも知れません。
『多崎つくる』という名前の退屈な旅にでる
そうです。まず最初にことわっておかなくてはいけないのは、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』はとても退屈な小説なのです。
読み進めるうちに世界に引き込まれて、時間を忘れて没頭してしまうような物語を求めている人には、はっきり言って向いていません。
私は、村上作品は最低でも2回は読まないと「本当の楽しさ」が分からないと思っているのですが、この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』に関しては、3回目くらいでやっとじわじわと面白くなってきました。
村上春樹さんの小説を読むことは、まだ行ったことの無い場所に、1人きりで旅立つことと似ています。
旅って、基本的に退屈じゃないですか。キレイな風景を見たり珍しい動物を見たり、胸躍る体験をするのがもちろん目的なのだけれど、それはほんの一瞬で、旅程で考えれば圧倒的に退屈な時間の方が多い。
それでも人は、退屈を持て余すために旅に出る。
そう、だから、退屈覚悟で行くのが旅であって、退屈覚悟で読むのが村上春樹さんの小説なんです。
なぜなら、退屈こそが人生において最も大切なことだから。
あらすじ『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』
多崎つくるは鉄道会社でエンジニアとして働きながら東京で暮らしています。子どもの頃から「駅」に魅せられ、「駅」を作る仕事に憧れていた彼にとって、鉄道会社で働けていることは夢が叶ったと言って良いでしょう。
お気に入りの駅はJR新宿駅で、特に用事もないのに新宿駅を訪れてホームに行き交う人々や電車を眺めることさえあります。
36歳で独身。これまでに数人の女性と恋愛をしてきましたが、自分をさらけだせるような信頼関係を築いた経験は1度もありません。
つくるには、心を許し合える恋人どころか、気の合う友達さえ1人もいないのです。
彼がそこまで人間関係に慎重になる背景には、過去の苦い経験がありました。
切り裂かれたグループ
多崎つくるは大学進学のために上京するまで、地元の名古屋で暮らしていました。
高校時代は男女5人の友人グループを作り、お互いを信頼できる仲間として意識していましたが、つくるだけが進学で上京することになったのです。
上京をしても、まとまった休みがあれば名古屋に帰り、グループの仲間に会いに行っていたつくる。彼にとって、4人はかけがえのない大切な存在でした。
しかし、ある日突然、そのグループから決別を言い渡されます。
「もうこれ以上誰の所にも電話をかけてきてもらいたくないんだ」
突然の宣告に彼は深く傷付きますが、なぜ自分が拒絶されたのかを確かめられないまま、年月だけが過ぎていきます。
結局、名古屋のグループとはそのまま別れてしまい、つくるは、「自分がどうして彼らから拒否されなくてはいけなかったのか」という疑問を持ち続けたまま大人になり、いつしか他人に心を開けなくなってしまったのでした。
それでも、心の傷を隠して自分なりの人生を全うしてきたつくるでしたが、ある女性と出会ったことで、止まったままの時計がようやく動き始めるのです。
彼女の助言に従い、名古屋のグループ1人1人に事情を聞きに行くことになった多崎つくる。そこで明かされる真実は、彼に大きな衝撃を与えることになります。
『色彩』とは何を意味しているのか
『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を解説するにあたって、まずタイトルに含まれる「色彩」と「巡礼の年」というキーワードの意味を解き明かす必要があると思います。
色彩とはもちろんカラー、色あい、なのですが、この物語の中での色彩について、少し説明しておきます。
まず、多崎つくるを人間不信(?)にした、名古屋のグループがありますが、このグループのメンバーの名前を紹介します。
赤松慶(あかまつ けい)
青海悦夫(おうみ よしお)
白根柚木(しらね ゆずき)
黒埜恵里(くろの えり)
男2人、女2人です。みんな名前に色が入っています。そしてそれを意識して、お互いをアカ・アオ・シロ・クロと色で呼び合っていたりします。
なので、名古屋の仲良しグループの中で多崎つくるだけが名前に色が入っていないわけです。
でも、そんなの別にどうだっていいじゃないかと思いますよね。ところが、つくる自身、これについて仲間はずれのような意識を持っているのです。
そして、つくるが名古屋のグループに拒絶された後、唯一、親密な付き合いのできた後輩の名前が灰田文紹(はいだ ふみあき)です。
また、色が入っています。その他にも、色がつく名前の人物が出てきます。
ということは、『色彩を持たない多崎つくる』は、名前に色彩がないという意味なのでしょうか。
いえいえ、それでは単純すぎますよね。
村上春樹さんはこれまでにも小説の中で「色彩」「カラフル」という言葉をよく使っていますが、それを細かく読み解くと、彼にとって「色彩」とは、人生の豊かさをあらわしているように感じます。
あるいは、自己肯定感がある人、つまり、自分にある程度の自信を持って人生を謳歌している人。
村上春樹さんは、そういう人を「色彩を持っている」と、あらわしているのではないでしょうか。
つまり、色彩を持たない多崎つくるとは、「自己を肯定できていない、自己認識の乏しい多崎つくる」と解釈しても良いのではないかと私は思います。
フランツ・リスト『巡礼の年』
名古屋のグループ以外で、つくるが親しい付き合いをできた唯一の人物が、同じ工科大学に通う2学年下の灰田文紹でした。
積極的な人付き合いは苦手とする2人でしたが、少しずつ心を許し合い、お互いを信頼するようになっていきます。
ある日、つくるのアパートに遊びにきていた灰田が、1枚のレコードをかけました。それがフランツ・リストの「巡礼の年」だったのです。
どこかで聴いたことのある曲に、つくるの心は揺れ動きます。
「僕の知っている女の子がよくその曲を弾いていたな。高校生のときのクラスメートだった」
つくるが高校生の頃、ピアノが得意だったシロがよく弾いていたのが、この「巡礼の年」に収録されている「ル・マル・デュ・ペイ」でした。
この「巡礼の年」がどうして物語のタイトルになっているのかといえば、ただ思い出の曲だったから、というわけではありません。
「巡礼の年」は、灰田とシロという2人の人物と多崎つくるを記憶の糸で繋いでいます。
それは、つくるにとって灰田とシロが「もう2度と会えない2人」という意味で、大切なポイントになっているのです。
青春の痛みと犠牲
多崎つくるは、名古屋のグループから拒絶され、深く傷付かなくてはならなかったことについて、「自分は犠牲になったのだ」と感じています。他の誰かを傷付けないために、グループを壊さないために、自分は犠牲になったのだと。
なぜ彼がそうした立場を引き受けなくてはいけなかったのか、はっきりと書かれてはいません。
しかし、おそらく作者は「色彩を持たない」という言葉の裏に、多崎つくるが犠牲に選ばれた理由を結びつけているのではないかと思います。
謎を解く必要はない
村上春樹さんの小説を読んで、「あれってどういう意味?」「結局どうなったの?」という疑問を持つ人がたくさんいるのですが、はっきり言うと、村上春樹作品に謎の答えは用意されていません。
このあとどうなったのか、なんて、村上春樹さんも分からないのです。
村上春樹さんが結末を考えずに小説を書き進めることは有名ですが、彼は書きながら物語の細部を理解し、それを言葉にかえていくのです。
なので、謎の答えなんて最初から存在しません。
『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を読んでいるとき、読者は多崎つくるになって、過去をめぐって自分を探してみてはいかがでしょうか。
大学のプールでハンサムな後輩と親しくなり、レクサスのショールームで古い友人に会い、フィンランドの木立の中に建つサマーハウスで十六年越しの愛を告白されるのです。
退屈だけれど色彩のある、そんな時間をきっと過ごせると思いますよ。