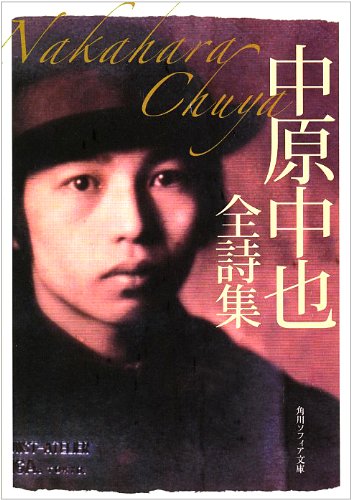村上春樹さん5作目の長編小説『ノルウェイの森』は、1987年9月4日に講談社から刊行されました。
1960年代後半の、村上さんいわく「ひどくシリアス」で、「人々はせっせと理想主義に燃えていた」世の中で、時代に少し取り残された若者たちの大きな喪失とそれを乗り越えた再生を、淡々と描きあげたリアリズム小説になっています。
村上春樹作品の中でも最も売り上げ部数が多く、文庫版も合わせると、その発行部数はなんと1000万冊以上。
日本国内だけでなく、世界中で愛され続ける名作。『ノルウェイの森』のあらすじと解説、名言をまとめました。
『ノルウェイの森』を百何万部も売ったことで、僕は自分がひどく孤独になったように感じた。そして自分がみんなに憎まれ嫌われているように感じた。
『ノルウェイの森』あらすじ
死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。
高3の春、キズキが自殺をした。突然親友を亡くしたワタナベは、自らの記憶から逃れるように、生まれ育った街を飛び出し東京の私立大学へ進学する。
キズキのいない世界でワタナベのやるべきことは、
「あらゆる物事を深刻に考えないようにすること、あらゆる物事と自分のあいだにしかるべき距離を置くこと」
それだけだった。
東京で寮生活を始めたワタナベは、中央線の電車の中でキズキの恋人だった直子と偶然再会をする。
直子もまた、キズキの幻影を封印するために東京に出てきていたのだった。
心に同じ傷を持つ二人は、毎週日曜日にデートをするようになった。ワタナベは直子に好感を持っていたが、直子との距離はなかなか縮まらない。
東京の町を一緒に歩きつづけるだけの時間を、ワタナベと直子は積み重ねていった。
どこに行きたいという目的など何もなかった。ただ歩けば良かったのだ。まるで魂を癒すための宗教儀式みたいに、我々はわきめもふらず歩いた。雨が降れば傘をさして歩いた。
村上春樹『ノルウェイの森(上)』より
直子と親密になればなるほど、「直子が求めているのは自分ではない」と実感するワタナベ。
直子が自分に何か伝えたがっていると考え、どうすれば良いか悩み、しかし直子を傷付けたくないという気持ちが先に立って、抱きしめてあげることさえ出来ないのだった。
日が昇り日が沈み、国旗が上ったり下がったりした。そして日曜日が来ると死んだ友達の恋人とデートした。いったい自分が今何をしているのか、これから何をしようとしているのかさっぱりわからなかった。
村上春樹『ノルウェイの森(上)』より
翌年の4月、直子の20歳の誕生日に二人は初めて性交するが、その後、直子はワタナベの前から姿を消してしまう。
直子から短い手紙が届いたのは7月の初めになってからで、そこには、大学を休学して京都の山中にある療養所へ入院することが書かれていた。
いろんなことを気にしないで下さい。たとえ何が起こっていたとしても、たとえ何が起こっていなかったとしても、結局はこうなっていたんだろうと思います。あるいはこういう言い方はあなたを傷つけることになるのかも知れません。もしそうだとしたら謝ります。私の言いたいのは私のことであなたに自分自身を責めたりしないでほしいということなのです。
村上春樹『ノルウェイの森(上)』より
ワタナベは直子からの手紙を何百回も読み返し、たまらなく哀しい気持ちになった。
直子の不在に茫然として、空虚な毎日を送っていたワタナベは、ルームメイトの男子学生”突撃隊”から、インスタントコーヒーの瓶に入った螢(ホタル)をもらう。
「これね、女の子にあげるといいよ、きっと喜ぶからさ」
”突撃隊”は不器用な優しさを残して山梨に帰郷し、そのまま寮へは戻って来なかった。
直子が去り、”突撃隊”が去り、1人ぼっちになったワタナベに、大学のクラスで顔見知りだった1年生の小林緑が話しかけてくる。
「孤独が好きなの?」と彼女は頬杖をついて言った。「一人で旅行して、一人でごはん食べて、授業の時はひとりだけぽつんと離れて座っているのが好きなの?」
「孤独が好きな人間なんていないさ。無理に友だちを作らないだけだよ。そんなことをしたってがっかりするだけだもの」と僕は言った。
村上春樹『ノルウェイの森(上)」より
直子への想いを胸に秘めながら、緑にも惹かれていくワタナベ。そんな中、入院中の直子の精神の病はしだいに深刻度を増していく。
「本当にいつまでも私のことを忘れないでいてくれる?」と彼女は小さな囁くような声で訊ねた。
「いつまでも忘れないさ」と僕は言った。「君のことを忘れられるわけがないよ」
村上春樹『ノルウェイの森(下)』より
森の中の療養所に直子を見舞いにいったワタナベは、同室のレイコさんの弾くギターを聴きながら、まるで孤立した3人家族のように、親密であたたかい時間を過ごすことになる。
レイコさんがギターで奏でるのはビートルズの名曲、「ミシェル」「ノーホエア・マン」「ジュリア」そして、「ノルウェイの森」。
「この曲聴くと私ときどきすごく哀しくなることがあるの。どうしてだかはわからないけど、自分が深い森の中で迷っているような気になるの」
村上春樹『ノルウェイの森(下)』より
ワタナベは直子を心から大切に想い、守ろうとするが、二人の愛は悲しい運命をたどることになる。
君に会えないのは辛いけれど、もし君がいなかったら僕の東京での生活はもっとひどいことになっていたと思う。朝ベッドの中で君のことを考えればこそ、さあねじを巻いてきちんと生きていかなくちゃと僕は思うのです。君がそこできちんとやっているように僕もここできちんとやっていかなくちゃと思うのです。
村上春樹『ノルウェイの森(下)』より
静寂の中で生と死を見つめて
誰でも1度くらいは、「死」について、想いを寄せたことがあるのではないでしょうか。
自分は死んだあとにどうなるんだろう?という疑問とともに、大切な人がもし死んだら、自分はどうすれば良いのだろう?という不安。
『ノルウェイの森』に描かれているのは、「最愛の人を亡くした時、人はどうあれば良いのか」という、喪失から再生への道しるべのようなものであると私は思います。
喜びの中には必ず悲しみが含まれているし、喜劇の中にも悲劇的な瞬間がある。そして、生の中に死は潜んでいる。
人は悲しい出来事を経験するたびに、その「真理」を、理解していかざるを得ないのです。
我々は哀しみを哀しみ抜いて、そこから何かを学びとることしかできないし、そしてその学びとった何かも、次にやってくる予期せぬ哀しみ対しては何の役にも立たないのだ。
村上春樹『ノルウェイの森(下)』より
村上春樹さんが直子やワタナベを通して読者に伝えたかったことは、この1文に込められているような気がします。
とり方によっては絶望的な言葉ですが、本物の悲劇に直面している人にとっては救いになる言葉だと思います。
『ノルウェイの森』の名言
『ノルウェイの森』に登場する魅力的な登場人物たちを、名言とともに紹介します。
ワタナベトオル(僕)
俺はもう十代の少年じゃないんだよ。俺は責任というものを感じるんだ。なあキズキ、俺はもうお前と一緒にいた頃の俺じゃないんだよ。俺はもう二十歳になったんだよ。そして俺は生きつづけるための代償をきちっと払わなきゃならないんだよ。
神戸の高校に在学中、親友キズキが自殺をして心に大きな傷を負う。東京の私立大に進学して学生寮で生活をする。
直子
「私のことを覚えておいてほしいの。私が存在し、こうしてあなたのとなりにいたことをずっと覚えていてくれる?」
キズキの幼なじみで恋人だった女性。
武蔵野にある女子大学に通っていたが、精神に不調をきたし休学。京都の療養所に入院する。
永沢
「ワタナベも俺と同じように本質的には自分のことにしか興味の持てない人間なんだよ。傲慢か傲慢じゃないかの差こそあれね」
ワタナベの学生寮の上級生で、東京大学法学部に在籍している。実家は病院を経営するエリート。
卒業後に外務省に入省する。
緑
「ビスケットの缶にいろんなビスケットがつまってて、好きなのとあまり好きじゃないのがあるでしょ?それで先に好きなのどんどん食べちゃうと、あとあまり好きじゃないのばっかり残るわよね。私、辛いことがあるといつもそう思うのよ。今これをやっとくとあとになって楽になるって。人生はビスケットの缶なんだって」
ワタナベと同じ大学に通う女学生。
入院している父親の付き添いと実家の本屋の店番を、姉妹で分担しながら生活している。
レイコさん
「あなたがもし直子の死に対して何か痛みのようなものを感じるのなら、あなたはその痛みを残りの人生をとおしてずっと感じ続けなさい。そしてもし学べるものなら、そこから何かを学びなさい」
療養所で、直子と同じ部屋で生活をしている患者兼ピアノ講師。
かつて夫と娘と幸せに暮らしていたが、ある出来事がきっかけで精神に不調をきたし、それが原因で離婚している。
2010年にトラン・アン・ユン監督で映画化
『ノルウェイの森』は、2010年にトラン・アン・ユン監督で映画化もされました。
私ははりきって見ましたが、映像は美しく、完璧に『ノルウェイの森』の世界を追求できていたものの、配役がちょっと合っていなかったかなと…少し残念でした。
松山ケンイチさんや菊池凛子さんは素晴らしい俳優さんですが、18~20歳のワタナベと直子を演じるには、どうしても違和感があったように感じました。
というのは、「幼さ」「未熟さ」が、この作品の中では大きなテーマとして扱われているから。
とはいえ、砥峰高原のススキが生い茂る美しい風景や、1960年代を再現した世界観は、さすがトラン・アン・ユン監督だなと思いましたよ。






![ノルウェイの森 [DVD] ノルウェイの森 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/519j7JHyQaL.jpg)