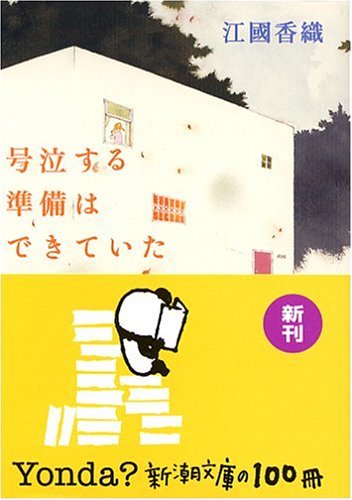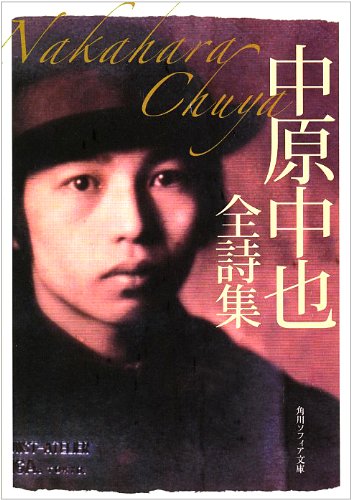江國香織さんの短篇集『号泣する準備はできていた』は、恋愛によって何かを、あるいは全てを、喪失してしまった女性たちの前進でも後退でもない淡々とした心象風景を描いた物語の詰め合わせです。
この小説は第130回直木賞を受賞したことも話題になったので、タイトルだけは知っているという人も沢山いるかも知れませんね。
お菓子の詰め合わせではなく、ひと袋のドロップ
江國さんはあとがきで、この短篇集を「ひと袋のドロップ」に例え、色や味は違っても成分や大きさ、丸さは大体同じものであると書かれています。
この短篇集に登場する女性たちはそれぞれ全く別の人生を歩んでいるわけですが、だからといって別次元の物語とは感じさせずに、たとえば同じ町内の誰かと誰か、または、同じ女子校に通っていた2人の女性が大人になった時の物語、というような、不思議なつながりを読んでいて感じさせられます。
ここからは、収録された12の短篇小説の中から、表題作『号泣する準備はできていた』のあらすじと解説をご紹介します。
江國香織さんの短篇の中でも「秀逸」という言葉がピッタリくる、本当に素敵な小説なので、その空気感が少しでも伝わればと想っています。
号泣する準備はできていた
売れない小説家の文乃は、一人旅で訪れたノーフォークで海辺のパブに住み着いている隆志と出会い、たちまち恋に落ちます。
「同胞にめぐりあった」という喜びで、きりもなく愛を重ねる文乃と隆志。
それはまるで「砂漠でまわり続けるスプリンクラー」のように、豊かな水滴をじゃんじゃんまき散らしながらお互いを貪欲に貪りあい、やがて、2人は一緒に日本へ帰国することに。
帰国後、アパートを借りて一緒に暮らし始めた文乃と隆志ですが、かつて、ふんだんできりもなく溢れていたはずのレンアイカンジョウは、突然、2人のもとから去っていってしまうのです。
他の女と寝てしまった、と隆志が私に謝ったとき、私は泣くべきだったのかもしれない。隆志が私より正直であるだけで、私たちは似た者同士なのだ。
「知ってるわ」
私は、でもかわりにそう言った。隆志は、
「やっぱりな、そうだと思った」
と言って弱く笑った。
「文乃には、なんでもわかられてしまう」
と。
私の心臓はあのとき一部分はっきり死んだと思う。さびしさのあまりねじ切れて。
別れたあともお互いを求め合い、身体を重ね続ける2人。愛し合った頃には2度と戻れないと分かっていても…。
「私たち、もうじき墜落するわ」
恋愛関係は終わってしまった、と、はっきりと認識しながら、それでも隆志を想い続ける文乃。
文乃にとって隆志は似た者同士の同胞であり、最愛の男であり、失ってしまった自分自身の輝かしい記憶の一部でもあり続けるのです。
私は隆志のやさしさを呪い誠実さを呪い、美しさを呪い特別さを呪い、弱さを呪い強さを呪った。そしてその隆志を心から愛している自分の弱さと強さを、その百倍も呪った。
日常の儚さと愛しさと
『号泣する準備はできていた』は、もちろん恋愛小説なのだけれど、メインに描かれているのは愛情云々ではなく、1人の女性の魂の軌跡というか、強く美しく生きる女性の儚くも愛しい日常が描かれているような気持ちもするのです。
たとえば、文乃が姪のなつきをバイオリン教室に連れて行く場面では、七歳のなつきの無邪気さや愛らしさをふんだんに織り込ませながら、いつか、なつきが大人になってたくさんの恋を経験して、文乃と同じように傷つき、傷つけながらも強く生きていくのだろうという未来を思い描くことができます。
強くなければ恋愛はできないから、「なつきが強く強くなってくれることを祈」る文乃は、それでも隆志との約束に胸をはずませながら、今日も夜の町を早足で駆け抜けていくのです。
江國香織さんの小説の世界に行ってみたい
私は長年、江國香織さんの小説を読みつづけているのですが、江國さんの小説というのはつねに「日常」を意識して書かれていると思うのです。
どこにでもありそうな町で、どこにでもいそうな男女が、ありふれた日常を淡々と送っている。
傷付いたり傷付けたりしながら、それでも、懲りもせずくっついたり離れたり、怒ったり笑ったりしている。
それは、もしかすると見慣れた光景なのかも知れないけれど、江國香織さんが描くことでキラキラとした魔法をかけられてしまうんですよね。
そうすると、目の前のリアルな日常までもが、まるで江國香織的世界のように光を浴びている。「あ、私の日常ってこんなに素敵なものだったの?」って、気付いたりする。
これがまさに、江國香織さんの小説の本当の魅力なのだと思っています。
「日常」に、つまらなさとか苦しさとか、そういう感情を持たざるを得ない生活を送っている人にとって、江國香織さんの小説はすごく救いになるような気がするのです。