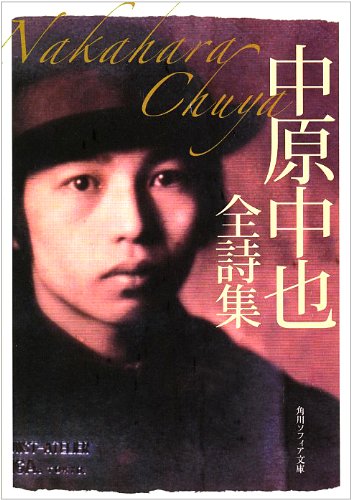Warning: Undefined array key 2 in /home/juicy18/senior-chiebukuro.com/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 66
もしも、自分の命の期限が分かったら、残りの日々をどう過ごせば良いのだろう。
長い人生の中で、自分の「死」について考えたことがない人なんていないと思います。人はいつか死にますし、それは大抵の場合、突然目の前に突きつけられるものです。
川村元気さんの『世界から猫が消えたなら』は、ある日突然「余命」を宣告された主人公が、残された日々の中で自分自身が存在していた意味を見つめ直す物語です。
それだけ聞くと、なんだかありがちの感動ストーリーかと思いますよね。でも、この物語はただ可哀想で苦しくなるような闘病ものとは全く違う、予測不能の面白さがたくさん秘められています。
あらすじ『世界から猫が消えたなら』
主人公の「僕」は30歳の郵便配達員。4年前に母親を病気で亡くし、それ以来、飼い猫のキャベツとの1人と1匹の生活をしています。
健康には特に問題なく暮らしていた主人公ですが、2週間にわたり頭痛と微熱が続いたことで、苦手だった病院へ。医師から告げられたのは、脳腫瘍で、余命は長くても半年だということ。
その夜、落ち込んでいた主人公のもとに『悪魔』があらわれ、「あなたは明日死にます」と告げ、死を先延ばしにしたいなら、世界から1日に1つずつものを無くしていくしかないと言うのです。
電話、映画、時計と、身近なものを次々に消しながら命をつなぐ主人公ですが、悪魔の「次に消すのは猫」という言葉で心が打ちのめされます。
自分が生きるために猫を消せば、大切な飼い猫のキャベツがいなくなってしまう。
キャベツのいなくなった世界で生き延びることに意味があるのか?
物語の途中、悪魔のはからいで人間の言葉を喋れるようになったキャベツと言葉をかわすうち、「世界に存在することの意味」を考え始めるようになった主人公。
世界から僕が消えたなら。
想像してみる。それは、どれほど不幸なことなのだろうか。
生きること、死ぬこと、誰かの心に残り続けること。世界に存在することの本当の意味に気付いた主人公が、最後に選ぶ未来とは。
いつか世界から消える日に備えて
いずれ自分が死ぬということは分かっていても、「明日死ぬよ」と知らされるほど不幸なことはないのかも知れないですよね。
『世界から猫が消えたなら』の主人公は、とりあえず悪魔のいいなりになって世界からものを消し去り続けるものの、それが一体何を意味しているのかを考える心の余裕はありません。
しかし、喋れるようになったキャベツと交流するうちに、かつて両親と交わした何気ない会話の全てに意味があり、自分にとって大切なことだったのだと気付くことができるのです。
”母さんは自分が旅に行きたいわけじゃなかった”
ただ僕と父に仲直りして欲しかっただけなんだ。
僕と父が最後に一緒に時を過ごし、話している姿を見たかっただけなんだ。
あぁ、と思わず声が漏れる。
なんで気付かなかったのだろうか。僕を産んでから、すべての時間を父と僕のためにささげてきた母さんが、最後の最後に自分のためにその時間を使うはずがなかった。
生と死は、命のある限りずっと向き合っていかなくてはいけない永遠のテーマです。
いつか世界から消える日に備えて、人はどうあるべきなのか。『世界から猫が消えたなら』は、日々の大切さと、自分が世界に存在している意味をあらためて考えさせられる小説です。